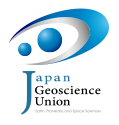付表2 中学校学習指導要領の内容から関連する専門分野の例
地球惑星科学に関連する中学校の教科、分野は以下の通り:
中学校「理科」の“第2分野”の地球
学年、単元名、関連する専門分野の例、内容
1年生 大地の成り立ちと変化
地質・地形・鉱物科学・堆積
・身近な地形や地層、岩石などの観察を通して、土地の成り立ちや広がり、構成物などについて理解する
古生物・第四紀など
・地層の様子やその構成物などから地層のでき方を考察し、重なり方や広がり方についての規則性を見いだして理解する
・地層とその中の化石を手掛かりとして過去の環境と地質年代を推定できることを理解する
火山など
・火山の形、活動の様子及びその噴出物を調べ、それらを地下のマグマの性質と関連付けて理解する
・火山岩と深成岩の観察を行い、それらの組織の違いを成因と関連付けて理解する
・自然がもたらす恵み及び火山災害について調べ、これらを火山活動の仕組みと関連付けて理解する
地震・活断層など
・地震の体験や記録を基に、その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気付く
・地震の原因を地球内部の働きと関連付けて理解し、地震に伴う土地の変化の様子を理解する
・自然がもたらす恵み及び地震災害について調べ、これらを地震発生の仕組みと関連付けて理解する
2年生 気象とその変化
気象・農業気象など
・気象要素として、気温、湿度、気圧、風向などを理解する
・気圧を取り上げ、圧力についての実験を行い、圧力は力の大きさと面積に関係があることを見いだして理解する
・大気圧の実験を行い、その結果を空気の重さと関連付けて理解する
・校庭などで気象観測を継続的に行い、その観測記録などに基づいて、気温、湿度、気圧、風向などの変化と天気との関係を見いだして理解する
・観測方法や記録の仕方を身に付ける
・霧や雲の発生についての観察、実験を行い、そのでき方を気圧、気温及び湿度の変化と関連付けて理解する
・前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づいて、その変化を暖気、寒気と関連付けて理解する
・天気図や気象衛星画像などから、日本の天気の特徴を気団と関連付けて理解する
・気象衛星画像や調査記録などから、日本の気象を日本付近の大気の動きや海洋の影響に関連付けて理解する
・気象現象がもたらす恵みと気象災害について調べ、これらを天気の変化や日本の気象と関連付けて理解する
3年生 地球と宇宙
惑星など
・天体の日周運動の観察を行い、その観察記録を地球の自転と関連付けて理解する
・星座の年周運動や太陽の南中高度の変化などの観察を行い、その観察記録を地球の公転や地軸の傾きと関連付けて理解する
・太陽の観察を行い、その観察記録や資料に基づいて、太陽の特徴を見いだして理解する
・観測資料などを基に、惑星と恒星などの特徴を見いだして理解する
・太陽系の構造について理解する
・月の観察を行い、その観察記録や資料に基づいて、月の公転と見え方を関連付けて理解する
・金星の観測資料などを基に、金星の公転と見え方を関連付けて理解する
3年生 地域の自然災害
火山・地震・気象・自然災害・リモセン・地理情報・応用地質・第四紀・地熱・地理・地形・雪氷・温泉など
・地域の自然災害について、総合的に調べ、自然と人間との関わり方について認識する